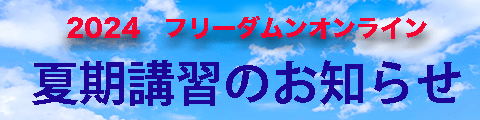塾に決められたペースは速い。
したがって、多くの子どもたちが、よくわからないまま、次に進んでいる。
スパイラル型カリキュラムだから、大丈夫、などと言われているが、その実、新たにいろいろ加わっていて、本当の意味でもスパイラルにもなっていない。
だから、ちゃんとわかる、次に進む、とできる方が本当は良いのです。
ということで、ペースの自由、というのをフリーダムオンラインのひとつのテーマにしています。
月例テスト5年生分を半年貯めた子も、63ぐらいの偏差値の学校に合格していったから、あまり、焦ってはいけないと思います。
最後、しっかり自分でやるようになると、面白いようにわかるようになるから、まず「わかる」を大事にしていきましょう。